気温35度を超える日が続く中、子どもがサッカーを続けていて心配…という保護者の声が増えています。真夏の炎天下での運動には、熱中症のリスクが常につきまといます。では、子どもにサッカーをさせるべきか?どんな条件なら安全なのか?この記事では、熱中症対策を中心に、保護者が知っておくべきポイントをわかりやすくまとめました。
子どもは大人よりも熱中症リスクが高い
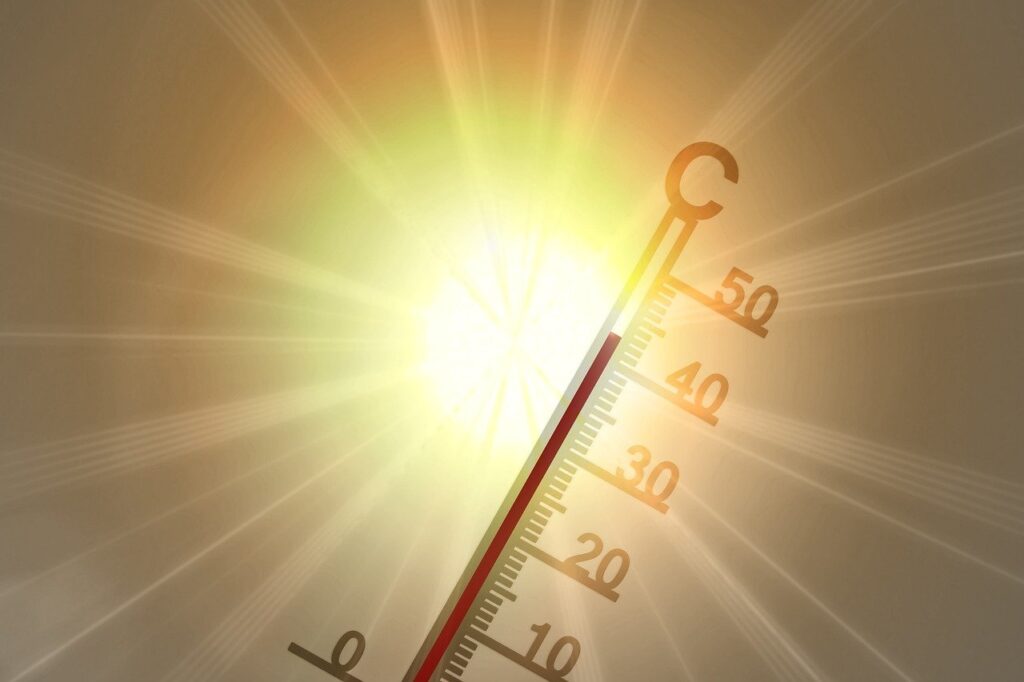
子どもは体温調整機能が未熟で、大人よりも暑さに弱いとされています。特に運動中は体温が上昇しやすく、こまめな休憩や水分補給を怠ると、あっという間に熱中症のリスクが高まります。
さらに、夢中でボールを追いかけていると「のどが渇いた」や「気分が悪い」といった体調の変化に自分で気づけないことも。そのため、周囲の大人が異変に早く気づくことが重要です。
「やらせない判断」も保護者の大事な役割

「暑くても頑張らせるのが美徳」という考え方は、時代遅れになりつつあります。現在では、炎天下でのスポーツ活動を中止・延期することは「正しい判断」として広く受け入れられています。
特に気温が35度以上、WBGT(暑さ指数)が31以上となった場合は、サッカーに限らず運動を中止すべきレベルとされています。これは、日本サッカー協会(JFA)のガイドラインでも明確に定められています。
「今日の気温は何度か」「日陰はあるか」「風は通るか」など、状況を冷静に判断し、場合によっては練習を休ませることも、子どもの健康を守る大切な選択肢です。
チームと保護者の連携も重要に

保護者個人の判断だけでなく、チーム全体として「無理をしない」「暑さへの理解を深める」ことが重要です。JFAも各クラブに対し、WBGT計を用いた計測、活動中止ラインの明確化、緊急時の対応マニュアル整備などを求めています。保護者は、練習予定が高温時間帯に設定されていないか、休憩が十分か、などを定期的にチェックし、必要に応じて指導者と連携する姿勢も求められます。
どうしても参加するなら、徹底した対策を

それでも「試合がある」「どうしても出たい」という日もあるでしょう。そうした場合は、以下のような対策が不可欠です:
- こまめな水分補給(15〜20分ごと)
- 氷や冷たいタオルを常備し、首やわきの下を冷やす
- 直射日光を避けるためのテントや日傘を用意
- 通気性の良いウェア、速乾性の高いインナーを着用
- 万一のために経口補水液や保冷剤を持参
また、家を出る前に「今日は体調どう?」と一言聞いてみることも、子どもの小さな不調に気づくきっかけになります。
サッカーと向き合う姿勢を、夏だからこそ見直そう

夏はサッカーの技術向上に最適な時期でもありますが、「健康を損なってまでやるべきか?」という問いは、常に立ち返るべきです。
特に小学生年代では、1回の無理が後のサッカー人生に影響することもあります。真夏のサッカーは、「やらせるべきか」「休ませるべきか」という選択が、保護者にとっての大きな判断となるのです。
そして、子どもにとって本当に良い経験となるかどうかは、暑さに耐えることではなく、体調と向き合うこと、自分の状態に気づけること、そして大人が見守っているという安心感にあります。
「夏のサッカーは命と隣り合わせ」と心得て

子どもにとってサッカーは楽しいもの。でも、真夏の炎天下では、その楽しさが一転して危険に変わることもあります。
「少し休ませてもいい」「今日だけ欠席させよう」と思えるかどうかが、子どもの命を守ることにつながります。
日々の天候、体調、そして試合や練習の重要度を総合的に見て、無理のない判断をする。それが保護者にとって何よりも大切な役割なのです。



コメント